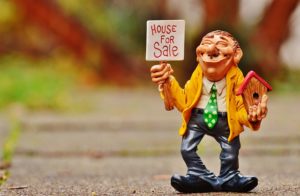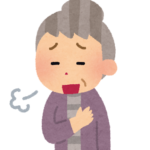土地をお持ちの方にとって、相続税問題は切実な課題です。「土地はあるけれど現金が少ない」ケースも多く、相続後に税金の支払いで困ることもあります。
多くの人が「相続=税理士に任せれば安心」と思いがちですが、実はそれだけでは不十分なケースもあります。
この記事では、税理士による相続“税”対策の落とし穴と、その上で検討すべき視点を整理します。
1. “計算だけ”重視の対策は不十分
- 多くの税理士は相続税をできるだけ少なくすること、評価を正確に出すことが主な業務範囲になりがちです。
- しかし、相続後の資産活用や土地の使い方などまでを見据えた対策がなされないことがあります。
- 税額を下げること自体は重要ですが、それだけで“相続後の未来”を守れるわけではありません。
2. 不動産・土地を持つケースの特殊性
- 土地が多いと現金で払えるだけの準備がないことが多い。
- 立地が悪く簡単に売れない土地を抱えていると、換金できず相続税支払いに困る。
- こうした土地をどう活かすか、価値をどう引き出すかがカギとなります。
3. “相続だけ”を見た対策のリスク
| 落とし穴 | 内容 | 被るリスク |
|---|---|---|
| 相続後の資産運用・収益性を無視 | 税金計算はできても、その土地をどう活かすかが抜け落ちる | 空き地化、税負担だけが残る |
| 評価だけ最優先 | 評価引下げに偏り、実際の活用が考慮されない | 利用・売却が難しく資産が休眠化 |
| 「税理士なら安心」という過信 | 税務以外の不動産・土地活用の知見不足 | 部分的な見落としが発生 |
4. “税理士以上”の視点を持つ必要性
- 不動産活用の視点:収益化・用途転換・賃貸や開発案件
- 流動性の設計:売却可能性や資金回収ルートの確保
- 将来シミュレーション:固定資産税・維持コストも含めた見通し
- 複合的な専門家との連携:税理士+不動産コンサル+法務など
5. (公認)不動産コンサルティングマスターの活用
不動産を多く持つ方の相続では、税理士だけでは十分にカバーできない部分があります。
そこで役立つのが(公認)不動産コンサルティングマスターです。
- 国土交通省・公益財団法人不動産流通推進センターが認定する専門資格
- 不動産の活用、相続対策、資産組み換えなどに精通
- 税理士と連携しつつ、実際の土地活用・収益化を含めた提案が可能
つまり、相続税の計算は税理士、不動産の有効活用は不動産コンサルティングマスター、というように役割を分担して協働させることで、より安心で実効性のある相続対策を実現できます。
6. 包括的なコンサルティング活用の流れ
- 現状把握:資産目録整理、現預金・用途見直し
- 税務シミュレーション:相続税の最適化、評価引下げ
- 活用プラン検討:売却・賃貸・開発の比較、収支シミュレーション
- 実行設計と実行支援:登記・許可取得、運用開始後フォロー
まとめ:バランスを持った対策を
税理士任せでは相続税を抑えられても、資産活用や将来設計を見落とす可能性があります。
特に土地を多く持つ方は、税務+不動産活用の両面から考えることが、後悔しない相続対策の鍵です。
そのために、税理士だけでなく、(公認)不動産コンサルティングマスターの協働を強くおすすめします。